| 現在、当分野では以下のようなテーマの研究をしています。 |
| ■ デンタルインプラント関連の研究 |
デンタルインプラントの生存率は10年後でも90%以上であり、とても良い治療であると考えられる反面、
色々なトラブルを抱えることも珍しくありません。
インプラントと骨がしっかりと密着する現象、それを維持するための生体反応、問題が起きた時の対処法などに
関する研究はまだまだ不十分です。 |
デンタルインプラントは欠かすことのできない補綴の一つのオプションです。
しかしながら生体レベルではわかっていないことも多いのが実情です。患者さんにより安心で安全なインプラント治療を提供するために我々は日々の臨床の疑問を解決すべく様々な研究に取り組んでいます。 |
| 1. 骨と力 |
●インプラントアバットメントスクリューの締め付けトルクおよび動的荷重付与が辺縁骨に及ぼす影響
●トルク値に応じたアバットメントスクリューの形態変化
●動物実験モデルを用いたオッセオインテグレーション崩壊機序の検索
●卵巣摘出ラットにおける荷重下インプラント周囲骨の組織学的観察 |
| 2. インプラントと骨質 |
●移植骨の骨細胞ネットワーク再構築と骨質に着目した自家骨移植の至適条件探索
●コラーゲンの架橋構造がラットのオッセオインテグレーションに与える影響
●移植骨と移植部位に骨質が与える影響に関する組織学的研究
●Effect of Collagen Cross-Link Deficiency on Incorporation of Grafted Bone。 |
| 3. インプラント表面性状と周囲の細胞 |
●GFPラットを用いたデンタルインプラント埋入および骨移植後における骨髄細胞遊走の組織学的観察
●インプラント表面性状と周囲に存在する細胞との埋入初期における相互作用
●Topography Influences Adherent Cell Regulation of Osteoclastogenesis |
| 4. その他(臨床研究) |
| ●新潟大学医歯学総合病院におけるセメント質骨性異形成症を有する患者に対するインプラント治療 |
|
|
|
| ●インプラントと力に関する研究 |
|
| ●インプラントと骨質に関する研究 |
|
| ●インプラント表面性状と周囲の細胞に関する研究 |
|
| ●オッセオインテグレーション機構解明に関する研究 |
|
| ●規格化ナノ構造チタンによる骨結合促進機構解明に関する研究 |
|
|
|
| ■ 歯根膜関連の研究 |
歯根の表面には骨との間に歯根膜というクッションが存在しています。
体の中でもとても特殊な組織で、その修復や維持は歯にとってとても重要です。
ところが、その特殊性故にまだまだ分からないことが多く、基礎的・臨床的な手法を用いた研究を行っています。 |
ひとの永久歯は一度失われると、自然に再生することはありません。そのため現在の治療法では、種々の人工材料によって補う方法が主流です(義歯、インプラントなど)。
わたしたちは、歯自体はこれまで通り人工材料を使用する傍ら、歯と周りの組織を結合する“歯根膜”を細胞生物学的な方法で再生することにより、天然の歯と遜色のない人工の歯の再生が可能になると考えています。そのための基礎研究として以下のようなものを行っています。 |
| わたしたちが歯根膜の研究で目指しているもの |
●力に対する歯根膜の応答の個人差を生む背景を解明
●天然歯における歯根膜の再生
●歯根膜を有した次世代インプラントの開発 |
|
|
| ●力に対する歯根膜の維持メカニズムに関する研究 |
|
| ●細胞外マトリックスによる歯根膜再生を目指した研究 |
|
|
|
| ■ 歯科金属アレルギー関連の研究 |
歯科金属アレルギーについても分からないことが多い、むしろほとんど分かっていないという現状で、
臨床データの収集や細胞レベルの基礎的な研究を行っています。 |
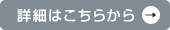 |
| ●金属アレルギーと乾癬に関する研究 |
| ●金属アレルギーとアトピー性皮膚炎に関する研究 |
| ●歯科金属アレルギーに関する臨床研究 |
|
| ■ 歯科理工学関連の研究 |
| 私達は「器材は歯学を貫く」という言葉のもと、歯科材料・器材の研究開発および評価等を行っています。 |
| ●SiC繊維強化型歯科用高分子材料とフェイスガード用材料の開発 |
| ●チタンスパッタによるメタライズを応用したジルコニアの表面改質 |
| ●CAD / CAM冠により適した支台歯形態の検索および評価 |
|
| ■ 歯根破折の治療に関する研究 |
日本や欧米では齲蝕や歯周病による歯の喪失は年々減少している中で、「歯の破折」による喪失は増加しています。
超高齢社会である本邦では補綴物の長期経過症例も増加しているため、今後歯根破折歯への対応とその解決策が求められています。 |
| ●歯根破折歯修復処置の臨床研究 |
| ●歯根破折歯に対する歯根膜再生法の開発 |
|
| ■ 歯学教育に関する研究 |
歯学部での学習は生涯学習の第1歩であり、とても重要です。
歯学部での教育が日本の歯科界を支えているといっても過言ではありません。
日々の教育に根拠をもって取り組み、より良い教育が提供できるよう、我々は学習方法による学習効果の
違い等に関して研究を行っています。また、海外との共同研究も行っています。 |
| ●治療計画立案能力における学習効果の検証 |
|
| ●総合模型実習におけるルーブリックを用いた評価とその信頼性の研究 |
|
| ●歯冠修復学実習における支台歯形成自己評価能力の研究 |
|
| ●疾患統合模型を用いた卒業時歯科臨床技能評価方法の開発 |
|
|
|
| ■ その他の基礎的・臨床的研究 |
| 自家骨移植や人工骨の研究、細胞移植の研究なども行っています。 |
| ●抗酸化物質を用いた骨増生法開発研究 |
|
| ●エピジェネティクス制御による骨造成法開発研究 |
|
| ●骨形成促進可能な骨造成法開発に関わる研究 |
|
| ●骨結合促進可能なジルコニアドリル開発に関する研究 |
|
|
|
